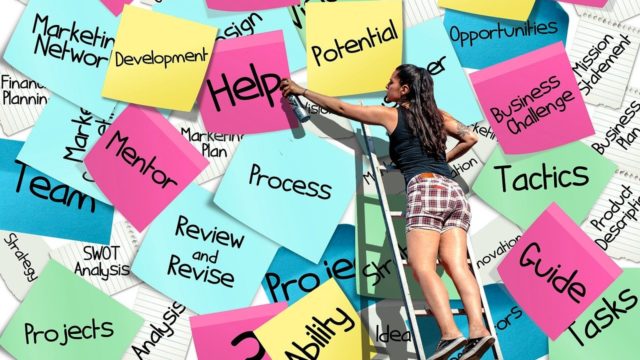こんにちは、のどかです!
実は我が家では、夫婦揃って育児休業(育休)を取得することにしました!
でも、男性の育児休業って、まだあまり馴染みがありませんよね。
もちろん私も、取得を本格的に考えて調べ始めるまでは、
まったくと言っていいほど制度や実態を知りませんでした。
そもそも、夫が育休をとることができるの?
お給料など収入面はどうなるの?
など、分からないことだらけでした。
今回は、そんな「パパの育休」について、
基本の知識を整理していきます!
パパはもちろん、
夫婦で育児に取り組みたいと考えているママさんにもぜひご覧いただきたいです!
そもそも育休って?
私と同じく新米パパさんは「育休ってそもそも何?」という状態なはずです笑
まずは基本的なところからいきましょう!
育休とは
かんたんに言うと育休とは、
子供が1歳になるまで育児のために休むことができる制度です。
これは、男女関係なく、法律で認められている制度です。
産休とは
「産休」という言葉も聞いたことがあるのではないでしょうか?
こちらは、赤ちゃんを産む女性向けの制度で、
産前6週、産後8週の産前産後に休みを取れるという内容です。
休みがとれる期間は?
育休と産休を使うことで、実際に休みが取れる基本の期間は次のようになります。
「取得可能」なだけで、期間内であれば短くなっても大丈夫です!
| 時期 | 女性 | 男性 |
| 産前6週 | 産前休業 6週 | なし |
| 産後8週まで | 産後休業 8週 | 育児休業 |
| 産後8週~子が1歳未満 | 育児休業 | 育児休業 |
ポイントとしては、
- 男性は産前の休業制度はなし
- 産後8週までは、男女とも休みが取れるが、制度の名前が違う
- 男女ともに、子が1歳になるまでが基本の期間
といったところでしょうか。
期間の延長は可能?
単純に「もっと期間を延ばしたい!」というのはできませんが、
- 保育園に子供を入れることができなかった
- 配偶者が亡くなったり病気などで、育児が困難になった
など、正当な理由があり、申請が認められた場合だけ、
1歳6か月になるまで期間延長ができます。
夫婦で一緒に取得できる?
結論から申しますと、できます。
育休制度は妻と夫それぞれに別々に適用されるものなので、
片方が取得したら、もう片方が取得できなくなるといったものではありません。
ですので、「妻が育休を取るから自分はムリだな」などと、
夫が取得をあきらめるようなことにはなりません!
また、夫が育休を取ることでさらに追加で使える制度もあります!
パパ育休
パパ育休とは、夫が育休を2回に分けて取得できる制度です。
主な使い方としては、
- 産後すぐの妻と子をサポート
- 子が1歳になるころ、育休から職場復帰する妻の代わりに育児に専念
というように、共働き夫婦がムリなく育児できるよう考えられている制度です!
制度を利用する条件は、
「産後8週間の間(=つまり産後休業の期間)に、夫が育休を開始しかつ終了すること」です。
パパ・ママ育休プラス
育休期間を子が1歳2か月になるまで伸ばす制度が、パパ・ママ育休プラスです。
- 配偶者がすでに育休開始済み
の時に、
- 子が1歳になるよりも前の日で、
- 配偶者の育休開始日よりも後から開始
という育休取得をすると、
後から取得した一人は、子が1歳2か月になるまで育休取得可能になります。
ポイントは、
- 夫婦で育休開始時期を少しズラす必要あり
- 後から取得開始した方だけが、延長可能
- 一人が取れる育休日数は1年間のまま(1年2か月に日数が増えるわけではない)
というところです。
収入はどうなる?
育休で一番気になるのが、お金面ですよね。
休み=働かなくなるので、収入ゼロになってしまうのでしょうか?
育児休業給付金
男女ともに、育休期間に国から支給される「育児休業給付金」というものがあります。
働けない期間収入ゼロでは、育児費用がなくなってしまうので、
なんと、国が補助してくれるんです!
もらえる金額は個人の収入によって変わります。
また、上限金額も設定されています。
ざっくりと計算する方法は、
- 育休取得前の6か月間の平均給与額がベース
- 育休開始~6か月間:ベースの67%
- 6か月以降:ベースの50%
というかんじです。
手取りではなく、額面!
もともとの収入の〇%と聞くと、
「やっぱり収入が下がるじゃないか」と思うかもしれませんが、
「額面」で計算されるのがポイントです。
つまり、税金が引かれる前の、残業代や各種手当などが足された金額がベースになります。
例として、
- 額面給与=35万円(基本給28万+残業代5万+住宅手当等、各種手当2万)
- 税引き後の手取り額=27万円
という収入だったとします。
細かい計算条件などは省きますが、
毎月この額の給与だったとすると、35万円の67%、
つまり、だいたい234,500円が、育児休業給付金の1か月分の支払い額となります。
普段手元に入る手取り額27万円とくらべると、
この例の場合、約86%は働かずに収入になるということです。
給付金は非課税
ふつう、お給料をもらうときに、
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料
引かれることになります。
税金ってものすごく高いですよね。
ですが、育児休業給付金は非課税です。
また、社会保険料が免除されます。
つまり、
- 所得税と住民税は支払う必要がなく
- 社会保険料は、払っていないのに納めていることになる
節税の面でも非常に効果が高い仕組みになっています。
注意点としては、
住民税だけは、前年の所得に応じて決まり支払うものなので、
支払わなくて済むのは来年となってしまう点です。
育児期間中には、前年分の支払いがありますので、
くれぐれも気をつけてください。
賞与は会社制度による
賞与=ボーナスについては、会社ごとに制度が異なるので
就業規則をよく確認しましょう。
ただし、多くの場合はマイナスになると考えていた方が無難です。
育休で休んだ日数に応じて賞与額が減額されたり、
単純に休みの期間分成果が出せていないためボーナス査定が相対的に下がる
など、マイナス要因が多くあるためです。
結論:制度をうまく活用して育児に参加しよう!
男性でも育休を取得できること、
最低限の収入は保証されることが、お分かりいただけたでしょうか?
もちろん、すべての人が育休を取得できるかというと、
難しいのが正直なところだと言えます。
ですが我が家では、
かけがえのない子供との時間が多少の収入減で買えるのであれば安いもの
と判断して、生後間もない子供の育児は夫婦で取り組もうと決めました!
知らなっただけで、育児をサポートする制度は年々良くなっているものはあります。
ぜひ皆さんも有効活用して、お子さんとの大切な時間をつくってみてはいかがでしょうか!
以上、男性の育児休業についてでした!